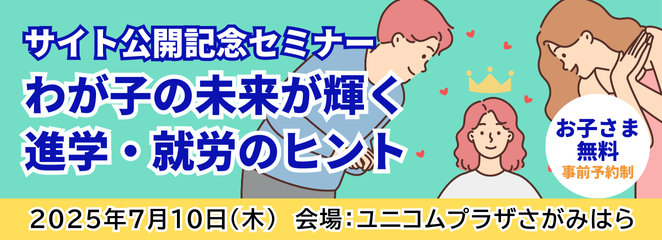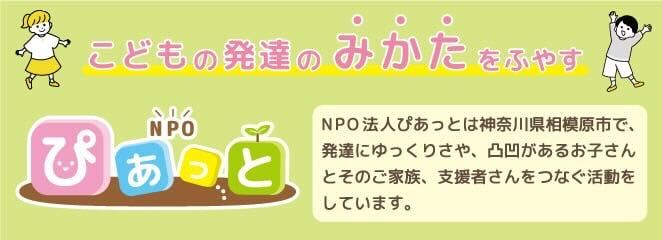前回は発達障がいのある子どもに対する「犬によるセラピー効果」について、「ストレスの軽減」、「情緒の安定」、「集中力の向上」、「社会性の向上」といった4つの効果があることをお伝えしましたが、今回はそのうち「ストレスの軽減」と「情緒の安定」について具体的にご説明します。
今回のお話の中では、 発達障がいのあるお子さんに対して「子ども」という言葉で表現していますが、年齢が大人になっていても同じことです。お子さんの体格が大きくなると、犬が威圧感を受けやすいことや、お子さんの力が強くなっていることへの配慮が必要になります。発達年齢や個性に合わせて、犬とゆっくりとした交流を増やしていくとともに、交流時に犬の様子を観察することが大切になります。

「ストレス軽減効果」って?
子どもが動物と一緒にいるとき、親は子どもが危険なとき以外は命令口調を封印しましょう。子どもが犬を強い力で撫でているときは、「やさしくね」と言って、お手本を見せてあげるとよいでしょう。親が楽しそうに犬を撫でる姿を見せることで、子ども自ら撫でたくなるような気持ちが芽生えます。生活の中で受け身になることが多い子どもたちも、犬の尻尾や耳をさわったり、手のひらの一部で背中を逆撫でしたり、“トントン”と軽く叩いてみたりするなどの行動が始まります。
犬の顔をさわるのが苦手な子どもは多いので、最初は広い背中からさわらせるとよいでしょう。子どもが犬との交流に慣れてくると、笑顔でいる親御さんともリラックスした親子関係がつくられていきます。そして犬がいるという環境が、子どものストレスを軽減することにつながっていきます。慣れないうちは、時間をかけてゆっくりと犬と同じ空間で過ごすことを心がけましょう。