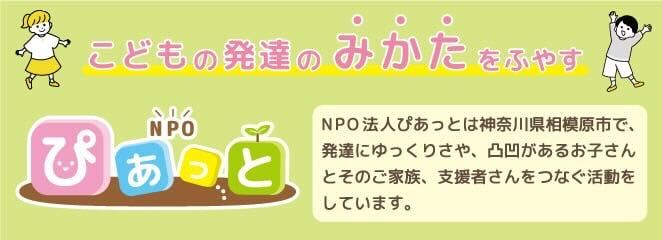前回は、発達に課題のある未就学の子ども(原則0~6歳まで)を対象にした「児童発達支援」についてお話ししましたが、就学されている小学生から高校生までの子どもを対象とした福祉支援サービスとして「放課後等デイサービス」があります。そして児童発達支援と放課後等デイサービスのことを「児童通所支援」と呼びます。これらは支援を受ける子どもの対象年齢に違いがありますが、どちらも子どもたちの発達を支援する大切な福祉サービス機関です。今回は、この2つの機関で具体的にどのような支援を受けることができるのか、またサービスを受けるまでのプロセスについて、お話しさせていただきます。

サービスの支援内容とは?
児童発達支援(療育支援)
児童発達支援では機能訓練を担当する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのスタッフにより、運動、コミュニケーション(発語・発音、あいさつや会話、相手の感情の理解など)、生活能力の向上などに対して訓練をしていただけます。また、機能訓練のスタッフ以外にも、保育士や看護師などのスタッフも常駐しています。なかには医療機関が事業所を運営している場合もあります。
サービスの提供時間には短時間(たとえば午前のみ、午後のみの数時間)、長時間(たとえば午前から夕方まで)という区分があり、短時間の場合は個別で集中的に、長時間の場合はさまざまなプログラムに取り組んでいただくことができます。
事業所によって提供しているサービス内容が異なる場合がありますし、前回お話ししたように「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」の違いもありますので、利用する際には事前に確認したほうがよいでしょう。
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスは、支援を必要とする障がいのある子どもや発達に特性のある子どもが通う福祉サービスで、6歳から18歳の就学児童(小学生、中学生、高校生)を対象に、授業終了後や休日に利用することができます。障がいのある子どもの生活能力の向上や社会との交流促進のために、さまざまなプログラムを通して支援を受けることができます。放課後等デイサービスも事業所によりサービスの提供内容が異なる場合がありますので、利用前に確認してみるとよいかもしれません。

児童発達支援(療育支援)と放課後等デイサービスの2つの支援の大きな違いは、前者が未就学の子どもが対象で、後者が学校に通っている就学児童が対象という点です。年齢に合わせたプログラムとなりますので、当然のことながら支援内容も変化していきますが、いずれも子どもたちへの訓練と、さまざまな支援を受けることができるという点では共通しています。
これまで何度かお伝えしてきましたが、これらの障害福祉サービスは各自治体の市区町村役場で受給者証を発行してもらうことでサービスを受けることができます。その際、障害者手帳や療育手帳は必要ありません。また、相談のみの場合は受給者証もいりませんので、お気軽にご相談してみてください。
表 児童発達支援と放課後等デイサービスの比較