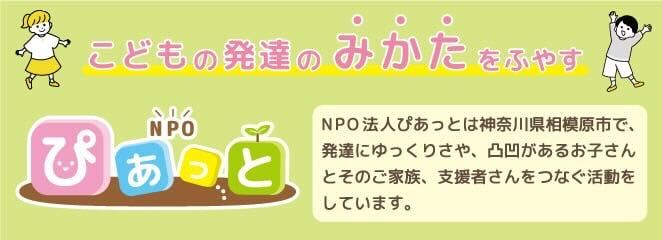今回は「児童発達支援」についてお話しします。児童発達支援とは、障がいがあったり発達に課題があったりする未就学の子どもたち(原則0~6歳まで)を対象に、日常生活で必要なスキルの習得や、集団生活での適応がうまく行えるような支援を行う福祉サービスのことです。児童発達支援ということばは、障害児福祉サービスのことをさす場合や、支援を行う施設のことをさす場合、あるいは支援自体をさす場合など、複数の意味で使われることがあります。
児童発達支援は障がいがあったり発達に課題があったりする小学校就学前の子どもたちを対象にしていて、「療育支援」と呼ばれることもあります。障害児といっても障害者手帳や療育手帳がなくても、児童相談所や医師などが必要だと認めれば利用することができます。
現在、児童発達支援を提供する福祉サービス機関には、「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」の2種類があります。それぞれについて詳しく説明します。

児童発達支援センターと児童発達支援事業所とは?
児童発達支援センターとは?
児童発達支援センターとは、子どもたちが定期的に通所して、自立するために必要なスキルや、日常生活に必要な基本的な動作やコミュニケーションのトレーニングなどの支援を行う施設です。
児童発達支援センターでは通所する子どもたちに療育を提供する以外にも、子どもが通う保育施設や地域の関係機関と連携をとりながらサポートします。専門性を活かして、子どもとそのご家族が地域で暮らしやすいように働きかけたりもしてくれます。
児童発達支援センターは自治体や社会福祉法人などが運営している場合が多く、いわゆる「中核的支援施設」といわれ、地域の中核を担う施設になります。
児童発達支援事業所とは?
児童発達支援事業所では、通所する子どもたちの発達支援や、ご家族への相談業務を主に行います。日常生活での困りごとや発達に関する不安に合わせて、子どもやご家族の状況に応じた計画を作成して支援します。
児童発達支援事業所と児童発達支援センターの違うところは、児童発達支援事業所は都道府県の指定を受けた事業所が運営できるということと、小規模なものから大規模なものまで、地域に多く存在するといった点です。こちらは施設というよりも「支援を受けることができる場」という位置づけになります。簡単に説明すると、児童発達支援センターは規模が大きくて幅広いサービスを提供する施設であるのに対して、児童発達支援事業所は地域に根差していて気軽に通える身近な場所という違いがあるといえるでしょう。
なお、児童発達支援には、「発達支援(本人支援・移行支援)」、「家庭支援」、「地域支援」といった3つの支援内容があり、障がいのある子どもやその家族に対して質の高い支援を提供するために定められた「児童発達支援ガイドライン」によって、その基準が定められています。これらの支援内容について、詳しくお伝えします。